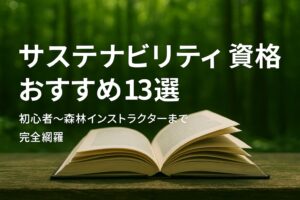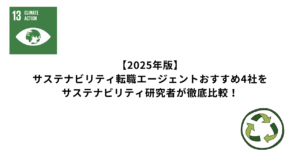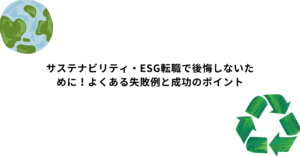この記事でわかること
・広報として積み上げてきたスキルを、サステナビリティ推進の現場でどう活かすか。
・企業価値と社会価値を両立させるために、どの知識を学び、どの順番で実務に取り込めばよいのか。
・広報→サステナビリティ領域への転職が一般的になりつつある今だからこそ、最初に抑えるべき学習ポイント
→TCFDやGRIといった国際基準から人的資本開示まで、公式情報を参照しながら具体的に整理します。
▼3日で読める!まずは転職前に抑えておくと便利なおすすめ書籍
広報とサステナビリティ推進はなぜ近いのか
広報の仕事は、社内外に「企業の物語」を伝えること。
サステナビリティ推進もまた、気候変動や人権といった課題に対して企業がどう向き合っているかを、投資家や顧客、従業員に理解してもらう営みです。
つまり両者は、伝える対象や使う言葉こそ違えど、「企業の存在意義をどう表現するか」という点で本質的に重なります。
習得すべきスキルの全体像
最初に理解しておきたいのは、サステナビリティ推進の言語は「基準」であるということ。
広報がプレスリリースの文法を知っているように、この領域では国際的な開示基準が“文法”として機能します。
代表的なのは、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言。
また、国際的なガイドラインとしてはGRIスタンダードやISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の基準が挙げられます。
いずれも公式サイトで全文が公開されており、学習に費用はかかりません。
おすすめはNoteBookLMを使って対象ページの内容を一気に要約させること
それだけで、概要と要点がつかめます!
代表的なサステナビリティ領域の国際基準一覧
ここに国内制度として人的資本やサプライチェーンの開示ルールが加わり、広報は「制度を翻訳し、経営メッセージに変える」役割を担います。
学び方のステップ
最初の一歩は、企業の統合報告書やサステナビリティレポートを読み込むことです。
自社だけでなく、業界リーダー企業のレポートを横断的に眺めると、どのようにESG課題が整理され、どんな表現で伝えられているのかが見えてきます。
次に、国際基準の公式文書を読みながら、自分の広報経験に結びつけて考えます。
「この開示項目は、プレスリリースのどの要素と似ているか」
「経営者インタビューで聞いてきた話を、サステナ文脈に置き換えるとどうなるか」
こうした翻訳作業こそがスキル習得の本質です。
実務での適用イメージ
例えば、人的資本開示。金融庁のコーポレートガバナンス・コードや経産省のガイドラインに沿って、人材育成方針やダイバーシティの状況を公表する流れが広がっています。
広報がここでできるのは、単なる数値の羅列を避け、「なぜその方針に至ったのか」「社員にどんな変化をもたらしたのか」を物語として編集することです。
また、TCFDの開示ではシナリオ分析という専門的な手法が登場しますが、投資家に伝わる形に翻訳するのは広報の腕の見せどころです。
リスクや機会を定量的に示す財務部門と連携しつつ、分かりやすい図解や社長メッセージに落とし込む。
ここで、かつて決算説明資料を作っていた経験がそのまま活きます。
今後のキャリアを見据えて
広報がサステナ領域に踏み出すとき、資格は必須ではありません。
ただし基礎知識を体系的に固めるには、サステナビリティ検定やESG関連の民間資格が役立ちます。
学びを通じて基準を理解し、実務で「伝える力」に変換していく。
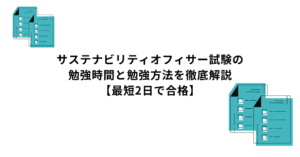
これができれば、企業と社会をつなぐ新しい広報の姿を描けるはずです。
まとめ
広報がサステナビリティ推進に入っていくことは、単なるキャリアシフトではなく、これからの時代に必然的な進化だといえます。
制度や基準の知識を吸収し、広報ならではの物語編集力で企業の取り組みを伝えていく。
その積み重ねが、社会から信頼される企業価値を形づくります。